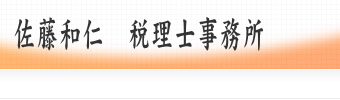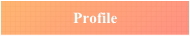アーカイブス
Address
佐藤和仁税理士事務所
〒980-0811
仙台市青葉区一番町1-15-33
TEL 022-265-0231
年末迄に出来る個人事業主の決算対策
 早いもので、今年も残るは1ヶ月となってます。税務・会計まわりではそろそろ年末調整の時期を迎えます。所得が給与のみの方は、年末調整で一年の所得税の精算となります(住宅ローン控除の初年度の方や医療費控除等ある方は確定申告が必要ですが・・・)。
早いもので、今年も残るは1ヶ月となってます。税務・会計まわりではそろそろ年末調整の時期を迎えます。所得が給与のみの方は、年末調整で一年の所得税の精算となります(住宅ローン控除の初年度の方や医療費控除等ある方は確定申告が必要ですが・・・)。
個人事業主の場合は、来年の2月16日から始まる確定申告で精算するのですが、個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日となるので、個人事業が黒字っぽい場合の対策は12月中に行う必要があります。そこで今回は、今からできる個人事業の黒字対策を書きたいと思います。
1.必要経費を増やす
個人事業(=事業所得)の所得計算は「収入」-「必要経費」ですので、「必要経費」が増えれば所得は減ります。
①少額減価償却資産の購入
青色申告をしている個人(従業員の数が1000人以下)が、30万円未満の減価償却資産を取得して業務供用した場合には、その金額全額を必要経費にすることが出来ます。パソコンやら備品やらの購入予定があるのであれば、年内中に購入して使い始めましょう。なお、年間で最大300万円までという上限があります。また、30万円未満かどうかは、消費税の経理処理が税込みの場合は税込み金額、税抜きの場合は税抜き金額となります。
②セーフティ共済
中小企業倒産防止共済と言うものですが、取引先が倒産した場合に掛けた金額の10倍までの範囲で回収困難となった売掛債権等の額以内の貸付を受けれる制度です。掛金は全額が必要経費になります。1月あたりの掛金は8万円が上限ですが1年分の前納も可能です(年最大で96万円)。掛金総額の上限は320万円となり、掛金納付月数が40ヶ月以上となると満額の解約金が受け取れます。
③短期前払費用
翌年以後の期間にかかる地代、家賃、保険料などを支払った場合には、その支払った金額をその期間に応じて按分し、各年に対応する部分の金額だけを必要経費に算入するのが原則ですが、これらの前払費用についてその支払った日から1年以内の期間分に相当する金額を支払い、支払った金額を継続してその年分の必要経費に算入しているときはその計算は認められます。
④65万円控除を使う
青色申告者の特典として青色申告特別控除があります。いわば領収証のいらない必要経費みたいなものなのですが、これらは
・簡易帳簿+損益計算書のみ作成:10万円控除
・複式簿記+損益計算書・貸借対照表を作成:65万円控除(山林所得は除く)
の2種類があります。複式簿記と聞くと眉をしかめる方もいらっしゃると思いますが、最近は使いやすい会計ソフトも多数ありますので、どうせ収入と必要経費の集計(即ち記帳)をしなければならないのですから、思い切ってチャレンジしましょう。
なお、65万円控除は確定申告期間内に確定申告書を提出する必要があります。10万円控除にはそういった規定はありません。
2.所得控除を増やす
所得税は「各所得の合計」-「所得控除額」の計算後の「課税所得金額」に対して税率をかけますので、「所得控除額」が増えれば税金が減ります。
①小規模企業共済
セーフティ共済と同じく中小機構が運営している制度です。常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員が加入できる退職金準備制度になります。掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象として全額が所得控除になります。月7万円が上限ですが1年分までの前納が可能です。一般の生命保険や個人年金の保険料を支払った場合の生命保険料控除よりも遥かに有利です。途中解約や契約者貸付金制度があり、掛金も年間の業績を睨みながらフレキシブルに変えられます。
②社会保険料の前納
社会保険の前納保険料は前納期間に対応して按分するのが原則ですが、前納の期間が1年以内の前納保険料については、その全額を支払った年の保険料の額又は掛金の額とすることが出来ます。これらの金額は社会保険料控除として全額が所得控除になります。健康保険や国民年金、国民健康保険などが該当します。本人と生計を一つにする配偶者や親族の分を負担した場合も同様です。
③未払の社会保険料を払う
社会保険料控除は、その年中に支払った額が全額所得控除となります。万が一、国民年金や国民健康保険の未払がありましたらこの機会に払ってしまいましょう。
④扶養親族を増やす
個人の扶養状態は年末の12月31日を基準にします。つまり、この日に扶養親族がいると扶養控除が受けられます。例えば年末に入籍した場合、配偶者の年収(給与のみの場合)が103万円以下であれば配偶者控除として38万円(配偶者の年齢が70歳以上の場合は48万円)が所得控除となります。
これらの対策を年内中に行うことが、個人事業の決算対策となります。黒字が見えている場合はこれらを検討されてはどうでしようか?
投稿者: 佐藤和仁 日時: 2008年11月28日 03:59